FETとヒートシンクを基板に固定するビス。絶縁処理が不要なポリカ製のを使った。
作業:2014/11 掲載:2014/12/01
図面の通りに組み立ててみた。
FETとヒートシンクを基板に固定するビス。絶縁処理が不要なポリカ製のを使った。
出力の取出しはピンヘッダを経由するようにした。
ATX電源コネクタ↓で直に引き出す方が簡単なのだが、
マザーボードによっては

こう↑なるおそれがあるので
こういうアダプタ↓を作って
どちらの向きにも対応できるようにした。
ATX電源コネクタ。ジャンク電源から切り離したもの。
24ピンでも20ピンでもよい。どうせ取り出す電流はたかがしれている。
このピンをすべて抜く。
抜き方だが、このコネクタのピンは、小さな「ベロ」2枚で外装プラスチックに引っかかる形で固定されている。
このベロを細い棒で押し込んでしまえば、するりと抜ける。
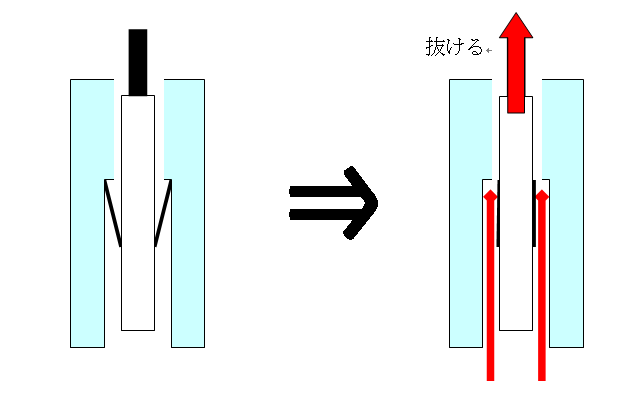
押し込んだベロは、ピンを抜いた後にちゃんと直す。
慎重にやらないと金属疲労でポロリと折れてしまうので注意。
あとは適切な長さに切って、フラットケーブルの対応する線にひたすらつないでいくだけ。
長さはフラットケーブルの線と、ATXコネクタピンの位置関係を確認しつつ、1本ずつ調節する。
(ATX電源コネクタのピンアサインは、検索すればすぐ見つかると思う。)
ハンダ付けしたところはもちろん、熱収縮チューブで絶縁する。
ジャンク趣味をやっていると、毎回のように必要になる作業だな。
「フラットケーブルの細い線が、電源の何アンペアもの電流に耐えられるだろうか?」
という懸念はもちろんあるが、そこはアマチュア。試してみてダメなら考え直せばよい。
当然、数本ずつパラ(並列)にする程度の配慮はしてある。
つなぎ終わったら各ピンをATXコネクタに差し込んでいき、フラットケーブルに40ピンコネクタをはめ込んで
余分なフラットケーブルを切り離せば完成。
何かと必要になる+12V(黄色)は、GND(黒)とともにもう1対取り出した。
40ピンコネクタはパーツ屋でももちろん入手可能だが、HARD OFFにジャンクでごろごろ出ている
40芯のIDEケーブル(懐かしい!!)から取り外したもので充分である。フラットケーブルも付いてくるし。
僕はそうした。
…この「取り外し」がものによってはまた面倒なのだが。
作った直後に気づいたが、アダプタについては改善の余地ありと思う。
この方法だと、フラットケーブルとATXコネクタ側のビニル線で硬さが大きく異なるため
フラットケーブルの芯にストレスがかかりがちとなり、すぐ断線しそうな感じである。
また、ATXコネクタと40ピンコネクタの間が、どうしても長くなってしまう。
試作なのでとりあえずはこのまま使うが、本チャンで使うときには作り直しだな。