FFCを買うときにあわせて買ってあった。

この小ささで 3[A]max の出力がとれる。
出力電圧は可変なので2個購入し、何かと便利な12V電源用としても使用することにした。
作業:2015/04 掲載:2015/04/29
USBの口が足りないので、USBハブを使うことは前述した。
このUSBハブはセルフパワー型なので、5V電源を用意してやる必要がある。
ハブの口数は4個。したがって電源の容量は
500[mA]×4個+ハブ自身の消費電流 = 2[A]+α
が必要、ということになる。
実はUSBハブを使うことはかなり早い段階から想定していて、それ用の電源モジュールは
FFCを買うときにあわせて買ってあった。

この小ささで 3[A]max の出力がとれる。
出力電圧は可変なので2個購入し、何かと便利な12V電源用としても使用することにした。
このモジュール、入力電圧 0.3〜28[V]の範囲で使えるので、19[V]のアダプタを使う本機にはちょうどいい。
ただし、外部入力によるOn/Off制御の機能がない。このままだとACアダプタを外さない限り
USBハブの電源が活きっぱなしになってしまう。
サーバーとしての使用(電源入れっぱなし)を予定しているので、実質ほとんど問題はないのだが、
やはりパソコン本体に連動して周辺機器もOn/Offしてほしいところだ。
このモジュールに使用されているIC「MP1584」のデータシートを読むと、2番ピンが「Enable」入力となっており、
このピンを浮かせるか、1.65[V]以上の電圧を印加するとOn、GNDに落とすとOff、という仕様のようだ。
このモジュールでは見たところ2番ピンは浮いており、つまり常時Onということになる。
そこでこのピンに、マザーボードのUSB端子から取り出した5V出力を供給してやることにした。
できあがりがコレ。
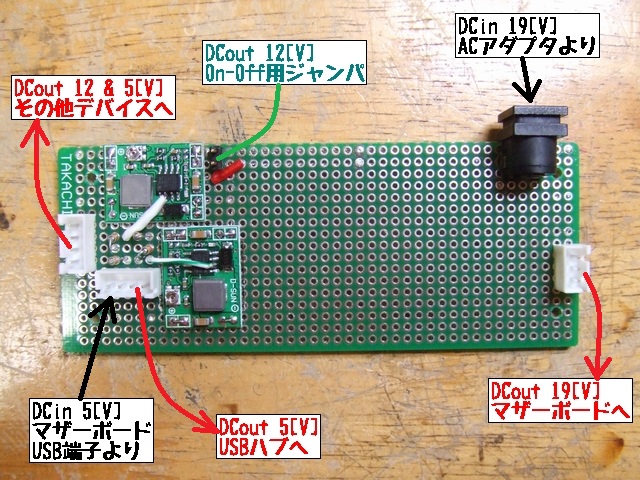
2番ピンに直にリード線をハンダ付けした。
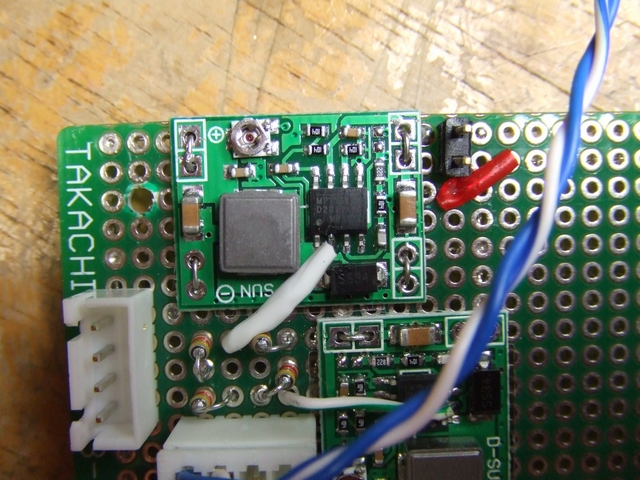
ピンのピッチは 1.27mm(1/20インチ)。毎度のことながらこういう細かいハンダ付けはホント疲れる。
PC本体のUSB出力から得た +5[V]を4.7[kΩ]の抵抗2本で分圧して、2.5[V]を印加。
わざわざ分圧する必要も無いと思うが何となく・・・である。
4.7[kΩ]という抵抗値に特段の意味はない。手元に何十本もあったので使った。
USB出力から5[V]を取り出すための分岐アダプタを自作。
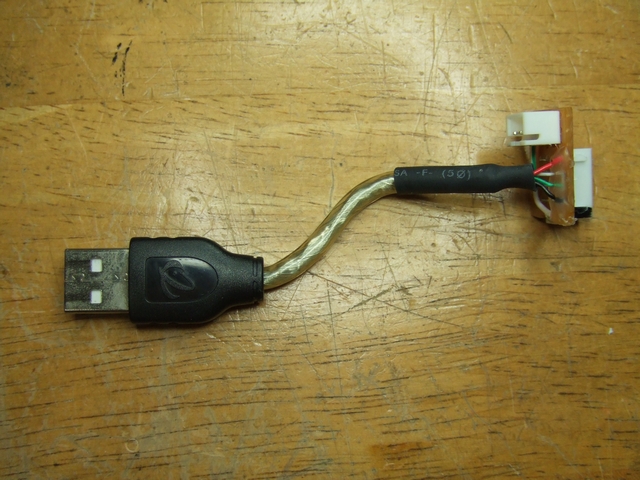
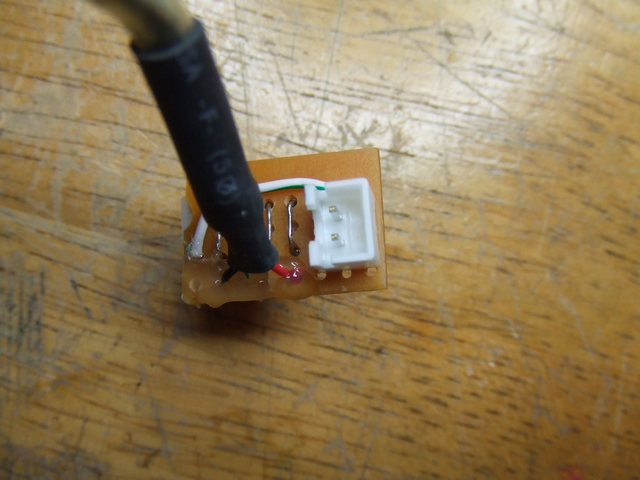
このUSBの信号ラインは、USBハブへの入力となるわけだが、前述の通りハブはセルフパワードであり、
この+5[V]はハブ側では使われておらず浮いている。
動作確認するの図。
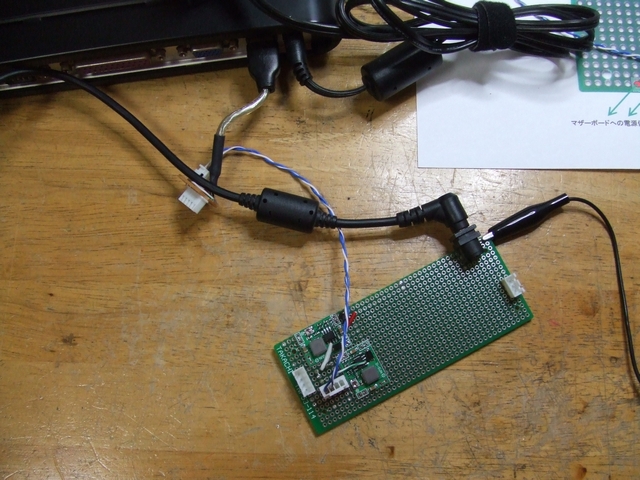
思惑通り、ホストとなるパソコンのOn/Offに連動して、電源出力もOn/Offすることを確認した。あー良かった。